Contents
体幹の弱さと向き合う日々 〜無理をしない回復の方法〜
はじめに
2015年、私は突然、心窩部(みぞおち)の激しい痛みで倒れました。
あの出来事を境に、私の体調は大きく変わり、その後の長い闘病と断薬の道を歩むことになったのです。
そして今もなお、その後遺症として残っているのが「体幹の弱さ」です。
ベンゾ離脱後に残った体幹の弱さ
長年飲み続けたベンゾジアゼピンを断薬し、離脱症状と戦った日々は、すでにかなり前のことです。
しかし、完全にすべてが元に戻ったわけではありません。
私にとって特に厄介なのが、体幹の弱さです。
体幹は、姿勢を支えるだけでなく、横隔膜を通じて呼吸や内臓機能にも深く関わっています。
少しでも負荷の高い筋トレをしたり、食べすぎたりすると、すぐに横隔膜に負担がかかり、
食欲不振や免疫力の低下といった不調が現れます。
無理な筋トレが体を壊す
実際、この2年ほど、私は何度も同じ失敗を繰り返してきました。
「筋肉をつければ体が強くなる」「筋トレこそ健康の基本」と信じて、
高負荷の腕立て伏せや懸垂を続けては体調を崩す──そんなことの繰り返しでした。
今思えば、体幹が弱い状態での無理な筋トレは、逆に負担を増やすだけでした。
ようやく、「筋トレは時期尚早だ」と自覚することができました。
体幹を守るために大切にしていること
体幹を守るには、まずは胃腸を休ませること。
私は以前から朝断食を取り入れていますが、これは大きな助けになっています。
朝食を抜くだけで、内臓への負担がぐっと減り、体幹が休まる感覚があります。
また、筋トレの代わりに取り入れているのが、負荷の低い運動です。
朝の散歩、ヨーガ、ストレッチ体操、ぶら下がり──
これらの緩やかな動きは、体に軽い刺激を与え、血流を促しつつ、過度な負担を避けてくれます。
安静と運動のバランス
「体調が悪いなら安静にすればいい」と言われることもありますが、
ただ寝てばかりでは心身ともに逆効果です。
動かなすぎれば、かえって筋肉は硬直し、心の張り合いも失われてしまいます。
だからこそ、緩やかに体を動かすことが大事だと、身をもって学びました。
無理に鍛えず、必要以上に頑張らず、適度に動き、休む。
このシンプルなリズムを繰り返すことが、今の私にとって最善の方法です。
無理をしない自然体の暮らし
最近つくづく思うのは、何かを「頑張ってやり遂げよう」と意気込むほど、
体に負担がかかりやすいということです。
とくに体幹が弱い私にとっては、その代償が大きいのです。
だからこそ、これからは「自然体」で暮らすことを何より大切にしたいと思います。
無理に鍛えるより、無理に働くより、無理に詰め込むより──
その時の自分の体の声を聞いて、心地よくいられる範囲で動く。
それが、遠回りのようでいて、最も確実な回復の道ではないかと感じています。
おわりに
2015年に倒れてから、私は体幹の弱さとともに生きています。
ベンゾを断薬したことは大きな一歩でしたが、その先に待っているのは、
薬に頼らない「本当の回復」を自分自身で築いていくという課題でした。
無理をしない、自然体で暮らす。
それは時に怠けているように見えるかもしれません。
でも、自分にとっては最善の治療法です。
今日も無理なく朝の散歩に出て、ヨーガで体をほぐし、体幹をいたわる──
そんな一日一日を積み重ねることで、いつか必ず元の強さを取り戻せると信じています。
💫 自分を追い込まない、頑張りすぎない。
この教訓を胸に、これからも体幹と上手に付き合っていきます。








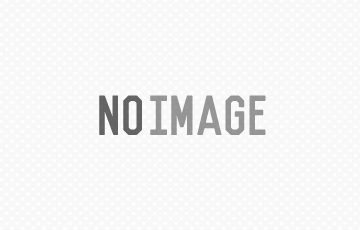






コメントを残す