Contents
📖目次
- AT式朝断食の経過報告
- 胃腸不調の正体──食べすぎという盲点
- 飽食の時代における断食の意味
- 「食べない勇気」と体の声を聴く
- 次のステップ──少食・断食の再挑戦へ
🍂本文
1. AT式朝断食の経過報告
先週お伝えした「AT式朝断食健康法」(→前回の記事はこちら)。
朝を抜き、昼を軽め、夕方は自由に──そんな生活を始めてみました。
ところが、現実はそう簡単にはいかないようです。
胃腸の調子はいまだ不安定で、心窩部に違和感が残り、
お腹の張りや食欲不振が続いています。
どうしても「食材の在庫整理をしなければ」と思い、
昼に食べすぎてしまうのです。
自分では軽めにしているつもりでも、実際にはカロリーも量も過多。
“食べすぎている自覚がない”ことこそ、慢性不調の根っこにあるのかもしれません。
2. 胃腸不調の正体──食べすぎという盲点
金曜日、少し腹を下しました。
一時的にはつらかったのですが、排泄のあと不思議と気分が軽くなりました。
腸が楽になると、心まで楽になる──そんな実感でした。
同時に「自分の胃腸には相当な負担がかかっていた」と気づきました。
飽食の時代に生きる私たちは、カロリーや栄養学の数字にとらわれ、
“必要以上に食べている”ことを正当化してしまいます。
朝断食をしているとはいえ、昼や夜に余分なものを詰め込んでしまえば、
それは単なる「朝抜きの食べすぎ」になってしまうのです。
この矛盾に気づいたとき、ふと「本格的な断食が必要かもしれない」と思いました。
3. 飽食の時代における断食の意味
過去をふり返れば、食べすぎて苦しみ、
ミニ断食を取り入れては忘れる──そんな繰り返しでした。
人は「食べることで健康を保つ」と思い込みがちですが、
実際は“食べすぎが毒”になることも多い。
体を痛め、心を鈍らせる原因の多くが、実は消化疲労にあるのではないかと感じます。
筋硬直や骨格の歪みが胃腸と連動しているように、
心身の調子は「食べ方」に強く影響されています。
飽食の時代にこそ、「食べない」という選択が
デトックスであり、精神のリセットになるのです。
4. 「食べない勇気」と体の声を聴く
お腹が空かないときは、無理に食べなくていい。
これは簡単なようで、意外に勇気がいります。
“栄養を取らなければ”“筋肉が落ちるのでは”といった
常識や恐れが頭をよぎるからです。
しかし、それらの考えこそが「現代栄養学の呪縛」かもしれません。
私は最近、体重が減少気味です。
そして、食欲のない日が増えると、
「もしかして病気なのでは?」「がんなのでは?」という不安さえ浮かびます。
けれど、冷静に考えれば、体が求めていないのに
無理に食べることのほうが、不自然です。
“空腹を受け入れる”ことが、実は最大の癒しなのかもしれません。
5. 次のステップ──少食・断食の再挑戦へ
筋硬直や骨格の歪みは、以前に比べてかなり改善しました。
だからこそ今は、「胃腸を整える」段階に入ったのだと思います。
慢性の不調や疲労感は、複雑な病ではなく、
単純に“食べすぎによる疲弊”である可能性もあります。
ここで一度、思いきって胃腸を休ませ、
体内の大掃除をする時期に来ているのかもしれません。
「食べる」より「食べない」こと。
「満たす」より「空ける」こと。
そのバランスを取り戻すことが、真の健康につながるはずです。
AT式朝断食健康法の次なるテーマは、
“少食と断食の融合”──食べない勇気を持ち、
体の声を静かに聴くこと。
この実践を通じて、
心と体の調和をもう一段階深めていきたいと思います。
📌まとめ
朝断食を続ける中で見えてきたのは、
「食べないことの難しさ」と「食べすぎの怖さ」でした。
体を守るための知識より、体の声に耳を傾けること。
それが、真の“健康法”の始まりなのかもしれません。









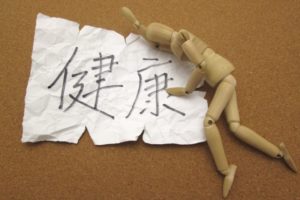





コメントを残す