Contents
季節の変わり目と体調管理──離脱後の筋硬直と向き合う日々
目次
- はじめに
- 季節の変わり目と体調の揺らぎ
- 風邪の症状と筋硬直のややこしさ
- 骨格の歪み改善という希望
- 鍼灸治療での回復と限界
- 無理な筋トレがもたらす悪循環
- 総合的なストレス管理の必要性
- 季節の変わり目が離脱者に厳しい理由
- 教科書ではなく「自分の経験値」に基づく養生
- 義務感や強迫観念から自由になること
- おわりに
1. はじめに
9月も下旬を迎え、朝晩は涼しくなってきました。しかし気候が穏やかになる一方で、体調面では揺らぎが目立ちます。私自身、この1週間は風邪のような症状が続き、食欲も落ち、背中や首の筋肉の硬直が強く現れました。
季節の変わり目は一般的にも体調を崩しやすい時期ですが、ベンゾジアゼピンの断薬後の回復過程にある身にとっては、さらに厳しい局面となります。
2. 季節の変わり目と体調の揺らぎ
日中はまだ汗ばむほどの陽気がある一方、朝晩は肌寒さを感じる。この寒暖差こそが、風邪を引きやすくする原因のひとつです。私も例外ではなく、のどの違和感や微熱感、食欲不振といった症状が続きました。
「涼しくなってきたからもう安心」と思った途端に崩れるのが、この時期の怖さです。
3. 風邪の症状と筋硬直のややこしさ
やっかいなのは、風邪による体のだるさや筋肉の張りが、ベンゾ離脱や後遺症として現れる筋硬直の症状と非常によく似ていることです。
「これは単なる風邪なのか?」「離脱症状がぶり返したのか?」と見極めが難しく、余計に不安や混乱を招きます。症状の重なりによって、体だけでなく心まで揺さぶられるのです。
4. 骨格の歪み改善という希望
一方で、回復の兆しも確かにあります。長年悩まされてきた骨格の歪みは、少しずつ矯正されてきており、姿勢や体のバランスは改善しています。
「骨格が整ってきている」という事実は、筋硬直やコリといった症状にも希望を与えてくれます。根本的に体の土台が安定すれば、症状も少しずつ緩和されていくはずだからです。
5. 鍼灸治療での回復と限界
鍼灸治療を続けてきたことも、改善に役立っています。施術後は筋肉の強張りが和らぎ、体が軽くなる感覚があります。ただし回復は一気に訪れるものではなく、少しずつ、階段を上がるようなプロセスです。
「すぐに完治を」と焦るのではなく、変化を積み重ねていく意識が必要だと感じます。
6. 無理な筋トレがもたらす悪循環
一方で、無理な筋トレは逆効果です。強い負荷をかければ、その場では「鍛えている」という充実感があるものの、翌日以降に強張りやコリが再発することがあります。
健康のための運動が、逆に症状を悪化させるという皮肉。大切なのは「頑張ること」ではなく「長く続けられること」だと、痛いほど学ばされます。
7. 総合的なストレス管理の必要性
季節の変化に体調を崩さないためには、単に運動だけでなく、食事・睡眠・心の持ち方といった総合的なストレス管理が欠かせません。
疲労が蓄積すれば免疫は落ち、栄養が偏れば回復は遅れ、心が焦れば体も固まる。要素はすべてつながっており、一つだけでなく全体を整える必要があるのです。
8. 季節の変わり目が離脱者に厳しい理由
一般の人でさえ体調を崩しやすい季節の変わり目ですが、ベンゾ断薬を経験した人にとってはさらに厳しいものとなります。離脱後の神経は過敏になっており、ちょっとした環境変化にも大きく反応してしまうからです。
「周囲の人は元気そうなのに、なぜ自分だけ…」と思うこともありますが、これは回復過程の特徴であり、焦る必要はないと自分に言い聞かせています。
9. 教科書ではなく「自分の経験値」に基づく養生
医療書や健康情報は参考になりますが、実際に自分の体で試し、経験してみないと分からないことが多いのも事実です。
「こうあるべき」という一般論よりも、「自分の場合はどうか」という経験値の積み重ねこそが最も頼りになると感じます。無理をして失敗したことも、今後の大きな学びとなります。
10. 義務感や強迫観念から自由になること
最後に改めて強調したいのは、「何かしなければならない」という義務感や強迫観念から自由になることの大切さです。
毎日散歩しなければ、筋トレを続けなければ、勉強を怠ってはいけない──そうした考えがかえって自分を追い込み、症状を悪化させることがあります。
「今日は休む」「今は静養する」と決めることも、立派な自己管理であり、前向きな選択です。
11. おわりに
この1週間は風邪のような症状に悩まされ、筋硬直も強く出ました。しかし同時に、骨格の改善や鍼灸の効果といった希望も感じています。
季節の変わり目は、ただ耐えるだけでなく「自分に合ったペース」を見直す好機でもあります。焦らず、無理をせず、義務感に縛られず、経験から学んだ工夫を積み重ねていくこと。
それこそが、長い回復の道を支える確かな歩みになるのだと思います。






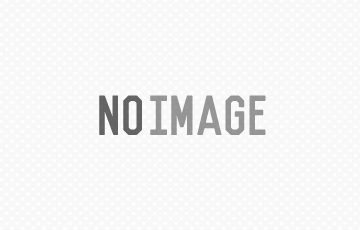








コメントを残す